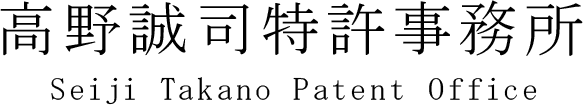第4次AIブームの幕開けとともに、生成AIが事実と異なる「作り話」を生成する、いわゆる「ハルシネーション」が問題になった。ハルシネーション(Hallucination)を日本語に翻訳すると「幻覚」である。2023年頃までは、ハルシネーションという言葉をよく目にし、耳にしたが、2025年になってからあまり見聞きしなくなった。
確かに、ハルシネーションの問題は減ってきていると思うが、無くなったわけではない。むしろ、局所的には大きな問題になっている。
ところで、1990年代、システム開発の現場では、オペレーティングシステム (OS) としてUNIXが普及していたが、そこに安価なWindows NT が登場した。バグが多く、OSとしては扱いにくかったが、次第にバグが減ってきて、多少のバグがあってもコストに見合うようになると、「そういうモノだ」と認知されていった。
また、それまで重要な通信を伴うシステムは、高価な専用線を敷設して構築されていたところ、インターネットが普及し始めた。インターネット通信はセキュリティに問題があったが、VPN(Virtual Private Network)技術によって、専用線の代替手段になっていった。セキュリティは十分とは言えず、伝送品質面でも問題があったが、技術の進歩によって改善され、不完全ながらも使用が許容されはじめ、次第に金融などのクリティカルな通信でも使われるようになった。
自動車における自動運転技術についても、事故ゼロのレベルになることはないだろう。それでも人が運転するより安全なレベルになっていく過程で、実用技術として社会に許容されていくに違いない。
新しい革新的な技術は、不完全な状態を許容する時期を経て普及していく。生成AIもその時期を今抜けようとしている。すなわち、ハルシネーションの言葉は残ると思うが、今後の技術進歩によって、ユーザーはある程度のハルシネーション発生を前提に利用し、「そういうモノだ」と、その問題に神経質にならなくなっていくと考えられる。
ハルシネーションと似て非なる問題として「フェイクニュース」がある。デマなど偽情報の類である。誤情報という観点でハルシネーションと共通するが、生成AIの利用者がそれを企図しているか否かの観点で両者の意味合いは大きく異なる。フェイクニュースが社会的な問題になっているため、相対的にハルシネーションの言葉の存在感がなくなっている側面もあるかもしれない。