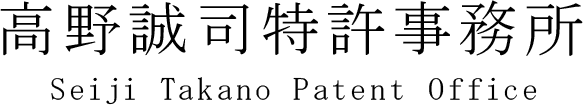とあるIPランドスケープに関するセミナーを受講して、思うところがある。具体的なセミナー名や固有名詞は伏せてその内容を紹介する。
あるサービスにおいて、圧倒的なシェア(約5割)を誇るA社が存在する。それをB社など3社が追従し、上位4社でおよそ9割のシェアを占める。更にスタートアップ企業やベンチャー企業が多数参入し、新規参入は後を絶たない。
私が受講したセミナーは、このサービスでは3番手に位置するB社の社員が講師(以下「講師C」)を務めた。B社は、IPランドスケープ活動の一環で、A社のアプリに関する知財について分析を行った。ライバル企業であるA社がいかに強力な知財網を構築しているか、ほめちぎり、惜しげもなく分析結果をセミナーで披露した。
講師Cは、事前に話す内容などセミナーの概要を所属組織に伝え、許可を得てセミナー講師を引き受けたはずである。私は、「ライバル会社であるA社の知財力を宣伝するような内容を、よく会社が許したな」と感心した。
そのセミナーは、知財関係者が多数受講していたので、講師Cの所属するB社とって、A社をはじめライバル会社の関係者も受講していたと思われる。
講師Cが意図していたか定かではないが、私は、このセミナーには、知財側面において戦略的な特殊効果があると感じた。本コラムでは、その効果について説明したい。
コトラーの競争地位戦略
このセミナーの戦略的効果を語る上で、予めコトラーの競争地位戦略について説明しておきたい。
「コトラーの競争地位戦略」とは、1980年にアメリカの経済学者のコトラーが提案した競争戦略の理論で、マーケットシェアの観点から企業を4つに類型化し、競争地位に応じた戦略目標を提示したものである。具体的には、マーケットシェアの大小に着目し、下表の通り類型化している。
コトラーの競争地位戦略
|
マーケット・リーダー |
最大のマーケットシェアを持ち、業界を牽引する主導的立場にある企業です。自社のシェアを維持、増大させるだけでなく、市場全体を拡大させることが戦略目標となります。 |
|
マーケット・チャレンジャー |
業界で2、3番手に位置づく大企業で、リーダーに挑戦しトップを狙う企業です。攻撃対象を明確にし、競合他社の弱点をつくなどしてシェアを高めることを戦略目標とします。 |
|
マーケット・フォロワー |
業界で2、3番手に位置づく大企業ですが、業界トップになることを狙わずに競合他社の戦略を模倣する企業です。製品開発コストを抑え、高収益の達成を戦略目標とします。 |
|
マーケット・ニッチャー |
シェアは高くありませんが、すきま市場(ニッチ市場)で独自の地位を獲得しようとする企業です。扱い商品の価格帯や販売チャネルなどを限定し、専門化することで収益を高めることを戦略目標とします。 |
出所:野村総合研究所 用語解説から抜粋
チャレンジャーの戦略
チャレンジャーの地位にある講師C所属のB社は、リーダーA社との差別化を図り、フォロワー企業のシェアを奪い、ニッチャーの本格参入を阻止したいところである。
このセミナーによって、A社の知財が広く詳らか(つまびらか)になった。講師CはA社の知財活動にリスペクトを示していたことから、A社の関係者は、B社がA社の知財権を侵害することはないと思ったはずだ。と同時に、今後B社が打ち出す新機能は相当の知財網を構築済と感じるに違いない。
そして、業界トップであるA社のサービスを模倣してきたフォロワー企業や、本格参入を検討しているニッチャー企業の関係者は、A社の圧倒的な知財力を知るに至り、事業の継続や参入のリスクを感じたに違いない。今後、サービスの一部中止や仕様変更を余儀なくされる可能性がある。
IPランドスケープセミナーの特殊効果
セミナーの主催者は、事例紹介など実践的なテーマで講演者を事業会社に依頼する場合、知財活動の誉れ高い企業を選別し、相応のポジションの者に打診するはずだ。したがって、事業会社の社員が講師を務める知財セミナーは、自社の知財戦略を誇らしく説明・宣伝し、話の中心は自社の知財活動になることが一般的だ。
ところが、このセミナーで講師Cは、自社であるB社の活動については抽象的な表現にとどめ、分析結果であるA社の知財戦略を解き明かし、具体的に説明した。
私は、講演者がライバル会社を褒め称える知財セミナーを初めて聞いた。まったく嫌味もない。そもそも、講師Cの所属企業であるB社が、それを許している懐の深さにも感服した。
このセミナーについて思うところとして、内容も興味深かったが、セミナーの構成自体が特殊効果をもたらすものと考える。すなわち、業界トップである他社の知財力を詳しく説明することで、受講したライバル企業を怯ませ(ひるませ)、自社の相対的な競争地位を向上させる、という斬新な知財戦略ではなかろうか。
弁理士 高野誠司